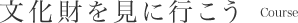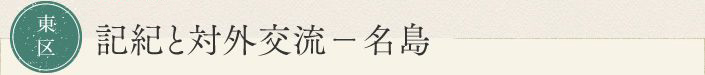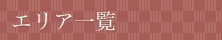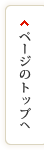- [1] 名島発電所跡の碑
・当時東洋最大と言われた火力発電所を偲ぶ記念碑です。大正9 年に第1 号発電機が竣工し、高さ61 メートルを誇る4 本の煙突が発電所の象徴となり、その姿は市内の至る所から確認できたと言われています。その煙突も1961 年(昭和36 年)から1962 年(昭和37 年)にかけて順次解体されました。現在、跡地は名島運動公園となっています。

- [2] 宗栄寺
・名嶋村の弁財天の別当寺であった神宮寺の末寺でしたが、明治初期の神仏分離令によって、この地に移されました。境内には神宮寺から移転された阿弥陀仏や文殊菩薩、新造された普賢菩薩の釈迦三尊像が祀られています。

- [3] 縁の石

- [4] 名島神社
・三韓遠征の無事平穏を祈って神功皇后が祈願成就のお礼として、この地に宗像三女神を奉納されたのが神社の起源と言われています。
・神功皇后にまつわる神社であることから、古より時の権力者が数多く参拝しています。もともとは、現名島公園(名島城跡)の場所にありましたが、天正6年豊臣秀吉により浜に下ろし移されました。

- [7] 砧板瀬
・皇后三韓へ御出立つの折り、供物を供えたところと伝えられています。
・御帰還の折りにも、凱旋の祝宴をしたといわれています。

- [8] 妙見島
・隆景が普請の陣頭指揮をしている所へ、神谷宗湛や嶋井宗室らが普請見舞いに酒や肴を進上し、島の海岸で酒盛りを開いたとそうです。
・豊臣秀吉も島津征伐や朝鮮出兵などで九州入りを何度もしていますが、名島城に来た時は、この島で茶遊会を開いたそうです。

- [9] 名島飛行場跡の碑・岸壁跡
・昭和5年開場された水上飛行場が名島飛行場です。4年後の昭和9年には閉鎖されていますが、その間にリンドバーグ機やツェッペリン号も飛来しています。その跡地を示す碑が建てられ、当時岩壁であった縁石が飛行場の名残として今も残されています。

- [10] 神宮寺跡の碑(お観音様)
・明治初年の神仏分離令により廃寺となった神宮寺跡を偲ばせるお観音様です。現在、観音さま広場となっています。お堂の傍には桜の木も立っています。

- [11] 岩見重太郎誕生之碑
・名島出身の武士で武者修行で妖怪やヒヒ、山賊などを退治したという伝説で小説や講談にもなった岩見重太郎の記念碑です。一説には架空の人物、あるいは元・小早川家臣で、夏の陣で戦死した薄田隼人と同一人物とも伝えられています。