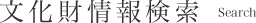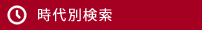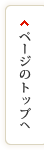橋本八幡宮のイヌマキ群落 
紹介文
イヌマキは、マキ科マキ属の常緑針葉樹である。暖地の常緑広葉樹林中に生育する。関東地方南部以西の本州、四国、九州、南西諸島に分布し、中国・台湾にも見られる。
橋本八幡宮のイヌマキ群落は、八幡宮境内から、北に隣接する須賀神社境内にかけて分布するもので、ご神木とされる夫婦マキを最大として、226本が群生している(2010年7月21日調査)。
両境内は、橋本緑地保全地区(0.4ha)に指定され、イヌマキ・クスノキなど20本が保存樹
に指定されている(内イヌマキは9本)。
ご神木である男マキは、境内の説明板によれば樹高20m、幹周り3.43m、女マキは樹高20m、幹周り3mで、福岡県下第5位、第14位のイヌマキ巨樹である。樹齢は400~500年とされる。
橋本八幡宮は、社伝によれば、文明14年(1482)に柴田蔵人佐繁信によって建立されたものとされる。橋本において誕生した福岡藩三代藩主黒田光之は、幼時を橋本で過ごし、寛文六年(1666)、西新町の紅葉松原に遷座したが、橋本の地いいの人々のたっての希望で、現在の地に社殿を再建したものであるという。
地図
近隣の文化財
近隣の文化財情報はありません。
- カテゴリーの紹介
 建造物
建造物 絵画
絵画 彫刻
彫刻 工芸品
工芸品 書跡・典籍・古文書
書跡・典籍・古文書 考古資料
考古資料 歴史資料
歴史資料 無形文化財
無形文化財 無形民俗文化財
無形民俗文化財 有形民俗文化財
有形民俗文化財 史跡
史跡 名勝
名勝 天然記念物
天然記念物 文化的景観
文化的景観 伝統的建造物群保存地区
伝統的建造物群保存地区 選定保存技術
選定保存技術 埋蔵文化財
埋蔵文化財 その他
その他