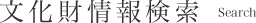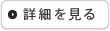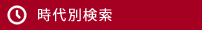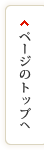はやま行事 
紹介文
旧暦10月19日(現在、11月19日)に奈多志式神社の秋大祭に奉納される行事。奈多にある西方、前方、牟田方、高浜の4地区のうちの2地区の若者が塩鯛を素早く料理して神に献饌する早さを競うものである。伝説では、三韓出兵に際して当地に軍議所を設けた神功皇后の饗応の奉仕が早魚行事になったと伝えられる。
19日朝、以前は問屋(木下家)または、尾形(浜崎家)の庭に臼を並べて畳を敷き、天井には帆布を張って(現在は鉄骨とテント張り)神楽舞台を作っており、ここが、行事の行われる「神楽座元」であった。現在は公民館に舞台を設置し行事を行っている。
午後5時頃、2地区のそれぞれで24・25歳の青年の中から籖によって「料理人」・「鰭さし」・「すり鉢かかえ」が選ばれる。出場者は民家に設けた「早魚宿」(現在は公民館)で古老の指導を受けて稽古を数時間続ける。かつては、その間に出場者の母親が一人で反物から早魚着物を仕立てたという。
10時頃、二組の出場者は神楽座元からの案内を受けて玄海に出て禊をする。宿で早魚着物に着替えてから座元に行く。
11時半頃、木下氏によって丹念に改められた鯛を捧持して出場者二組が舞台に並ぶ。「見事な御魚、お料理なされ」の合図で料理が始まる。鰭・頭を切り落とし、三枚に卸す。鰭は切り落とした時点で、「鰭さし」が「鰭受取」(神楽座元の主人)に渡す。早く渡した方が勝ちとなる。勝った地区には豊漁が約束されるのである。後に、鰭は女竹12本(月の数)に添えて神楽「鰭舞」の採り物となる。翌日、エビス祭りの後、海に納める。
当地は、南北に海を有する漁村である。伝承では、行事に関連して網元同志の漁場の優先権をめぐっての争いを伝えている。この点からみると早魚の行事は人為では決定しがたい事象を神慮に委ねることにより合理的な解決を図ろうとした共同体の心意が生み出したと考えることも可能であろう。また、この行事が年齢組織である青年会の卒業を意味し、「早魚を切る」ことが一人前と見なされる条件となっていたことも民俗行事として見逃せない点である。
地図
近隣の文化財
- カテゴリーの紹介
 建造物
建造物 絵画
絵画 彫刻
彫刻 工芸品
工芸品 書跡・典籍・古文書
書跡・典籍・古文書 考古資料
考古資料 歴史資料
歴史資料 無形文化財
無形文化財 無形民俗文化財
無形民俗文化財 有形民俗文化財
有形民俗文化財 史跡
史跡 名勝
名勝 天然記念物
天然記念物 文化的景観
文化的景観 伝統的建造物群保存地区
伝統的建造物群保存地区 選定保存技術
選定保存技術 埋蔵文化財
埋蔵文化財 その他
その他