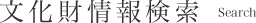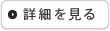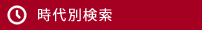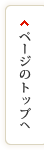ツクシオオガヤツリ 
紹介文
ツクシオオガヤツリはカヤツリグサ科カヤツリグサ属の多年草の一種である。我が国では極めて珍しい植物で、福岡城のお堀で最初に発見されたため、和名にツクシ(筑紫)の名が冠され、また他のカヤツリグサ類に比べて、著しく大型のためツクシオオガヤツリと呼ばれるようになった。分布が極めて限られるため発見されてから、長く植物学者の関心を集めていた植物である。秋には地上部が枯死するが、地下茎は生きていて春には叢生し、茎は高さ1~1.5mに伸び三稜形をしている。カヤツリグサ科は茎が三稜なのが特徴であり、これを両端から裂くと二裂せず、四辺形をつくり、その形が蚊帳を連想させることから一般名としてカヤツリグサの名前が古くからあった。その仲間はカヤツリグサ科として分類学でまとめられているが、世界には5000以上の種があるとわれるほど大きな科であり、日本では属で20以上、カヤツリグサ属だけでは25以上の種が分布している。
それらの中で特に大型なのがツクシオオガヤツリである。9月から10月に稈の先端から大きい穂が出て種子を作り、多量に散布される。湿生地、堀、治、池の泥土に好んで生育し、大きな株をつくって繁茂する。
明治39年9月1日、世界で初めて福岡城のお堀で発見された植物ということで特に福岡市の植物研究者の関心をひいてきた植物であり、研究もされてきた。
明治39年当時東京帝国大学理科大学の助手であった牧野冨太郎氏が釆福して指導した植物夏期講習会の折り、福岡城のお掘で一行が発見し、牧野氏が仮にツクシガヤツリと命名しその後、昭和6年に植物学者大井次三郎氏が当時のカヤツリグサ属の権威であったドイツのキューケンタール氏に標本を送付したところ、新種と鑑定され、大井の名をつけた新しい学名が与えられ和名もツクシオオガヤツリとなったという。この基準標本は福岡城の掘から採取されたものである。
熱帯のマレーシア、インド、インドネシアなどで限られた分布があるというが、それ程広い地域ではなく、我国ではほとんど福岡市に限られている。原品発見地の城内の堀の他に城南区、東区、南区、早良区などのため池に発見されているが、環境に神経質で、泥土の環境が変ると消滅することも多く、また他種との競合にも弱い。従って発見以後、消滅したり、再び増殖したり、新しい分布地が見付かったりしてきた。
天然記念物としては城内の掘に分布するツクシオガヤツリということであるが、堀の清挿その他による環境変化で、分布は一定しない。平成元年の調査では、裁判所に向って左側の濠に3株、右側の濠に4株、福岡城西南角で護国神社前の小池に25㎡ほどが残存しているに過ぎない。城前面の7株は市の保護の下で管理されているものであり、西南角小池はショウブ池とし種々人為が加えられた水面の縁に生き残っていて、いずれもかなり不安定な植生である。
地図
近隣の文化財
- カテゴリーの紹介
 建造物
建造物 絵画
絵画 彫刻
彫刻 工芸品
工芸品 書跡・典籍・古文書
書跡・典籍・古文書 考古資料
考古資料 歴史資料
歴史資料 無形文化財
無形文化財 無形民俗文化財
無形民俗文化財 有形民俗文化財
有形民俗文化財 史跡
史跡 名勝
名勝 天然記念物
天然記念物 文化的景観
文化的景観 伝統的建造物群保存地区
伝統的建造物群保存地区 選定保存技術
選定保存技術 埋蔵文化財
埋蔵文化財 その他
その他